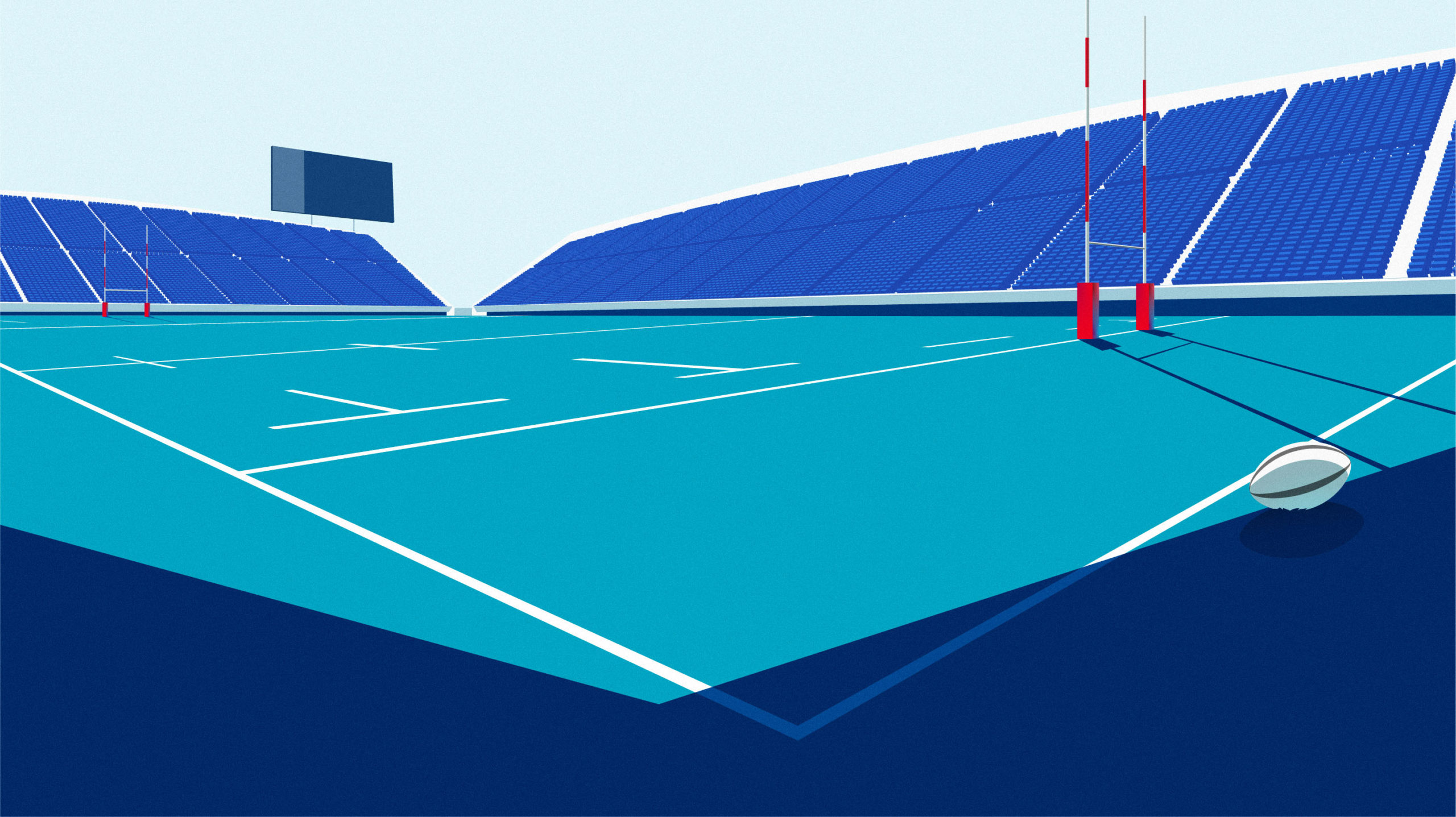ラグビー日本代表では多くの海外出身選手が活躍している。2021年度のラグビー日本代表では、メンバー37人中16人が海外出身選手(2021年10月30日現在)となっていて、他のスポーツと比較しても群を抜いた数字だ。
なぜこんなにも多いのか。戦力補強の側面があるのは当然として、その背景を紐解いていきます。
背景①ラグビーが「国籍主義」ではなく「協会(地域)主義」だから
まず、大前提としてラグビーの代表資格が、国籍主義ではなく協会(地域)主義であることがあげられる。
ラグビーはイギリスで生まれ、ニュージーランドや南アフリカなど"大英帝国"の植民地で広まっていきその中で協会が設立され、対抗戦が行われるようになったという歴史がある。イギリス内でも、イングランド、ウェールズ、スコットランド、アイルランドといった地域ごとに協会が独立している。

代表チームの構成を国籍で区切るという考え方がないのだ。現在のワールドラグビーの規定でも代表チームへの資格について国籍への言及はなく、「当該国で出生している」ことが第一条件になっている。
ワールドラグビー「競技に関する規定」 第8条 プレーヤーの身分、契約および移動の項を見てみよう。
8.1 本規定8.2の制限のもと、プレーヤーは、以下の条件を満たす一国の協会のシニアの15人制代表チーム、そのすぐ下のシニアの15人制代表チーム、または、シニアの7人制代表チームのみで、プレーすることができる。
(a) 当該国で出生している、または、
(b) 両親、祖父母の1人が当該国で出生している、または、
(c) プレーする時点の直前の60ヶ月間※1 継続して当該国を居住地としていた。
出典:ワールドラグビー競技に関する規定第8条「国の代表チームでプレーする資格」
8.1 (a) が今言及した所。そして8.1 (c)がポイント。日本代表に当てはめれば、外国籍で海外生まれであっても「5年以上日本に居住し国内でプレー」することで日本代表の資格が得られるのだ。
高校からの留学生は大学卒業後に資格を得、また社会人チームに補強として加入した選手も5シーズン在籍することで資格を得ることができます。
8.1 (c)の期間は以前は「36ヶ月」でしたが、2022年1月1日の改正で「60ヶ月」に延長されました
背景②"そろばん留学"からつながるトンガ王国との太いパイプ
日本代表の海外勢の中でも多いのがトンガ出身の選手だ。2019年W杯で活躍したヴァルアサエリ愛、中島イシレリ、今まさに売出し中のデビタ・タタフ、シオサイア・フィフィタらは全員、高校・大学時代に日本に留学生としてやってきた。
古くから日本の学生ラグビーはトンガ王国からの留学生を受け入れてきた歴史があるのだ。
始まりは"そろばん留学"。 歴代のラグビー日本代表海外出身選手にインタビューを重ねた、山川徹氏の著書『国境を越えたスクラム』(中央公論新社)の記述を参考にすると、1975年に大東文化大学ラグビー部がニュージーランド遠征した際に、ラグビー部部長の中野敏雄氏がトンガに足を延ばしたことがきっかけとなり、トンガ王室との交流が生まれたという。
当時のトンガ国王は大の日本びいきで、宮廷でそろばんの大会などを開いていた。やがてそろばん指導者育成のためにトンガ人青年を日本に留学させる計画が持ち上がり、ノフォムリ・タウモエフォラウと、1歳年下のホポイ・タイオネという2人が送り込まれた。1980年代と今から40年近くも前の話。そして前者のノフォムリは卒業後三洋電機でプレーし日本代表にまで上り詰めていったのだ。
そこから、高校・大学にトンガの有望なラグビー選手が日本に留学し、卒業後も日本に留まって社会人・代表でも活躍していくという流れが生まれた。
学校レベルでは、大東文化大学や正智深谷高校が長年トンガ留学生の一大受け入れ地となっていた。現在はとくに日本航空石川高校(前述フィフィタの出身校)や目黒学院高校(前述タタフの出身校)が有力なトンガ留学生を受け入れている印象がある。
背景③日本ラグビーのレベルアップ
最後に日本ラグビーのレベルが上がり、日本代表に憧れを持つ海外出身選手も多くなっている。
日本代表のスクラムを最前線で支える具智元は韓国出身。父親・具東春氏は1980年代~1990年代に韓国代表のプロップとして活躍したレジェンド。

具智元も当然、韓国代表を選ぶ道もあったが、「ずっと日本代表に憧れていましたし、お父さんも『日本代表を目指しなさい』と応援してくれ」日本代表を選んだという。
現在ラグビー日本代表は世界ランキング10位に入り、アジアの中では抜きん出た存在。 具も、韓国代表が強ければ母国の代表になる道もあっただろう。しかし。現在韓国は日本に大きく差をつけられてしまっている。ワールドカップに出場するには日本代表を倒す必要があるが、その可能性はほぼゼロ。レベルが高く、世界へ挑戦できる日本ラグビーに魅力を感じたのだろう。
では、日本ラグビーが今後さらに強くなれば8~9割が海外出身選手になるのもあり得るのか。規定を参照した通り、理論上はあり得る。ただ、現在のメンバー比率を見ても、海外出身選手が過半数を越えないような"自主規制"が働いているように感じる。「ラグビー日本代表はガイジンが多すぎる」と一部に揶揄するような声があることも確かであり、日本代表の海外出身比率は今後も議論されていきそうだ。