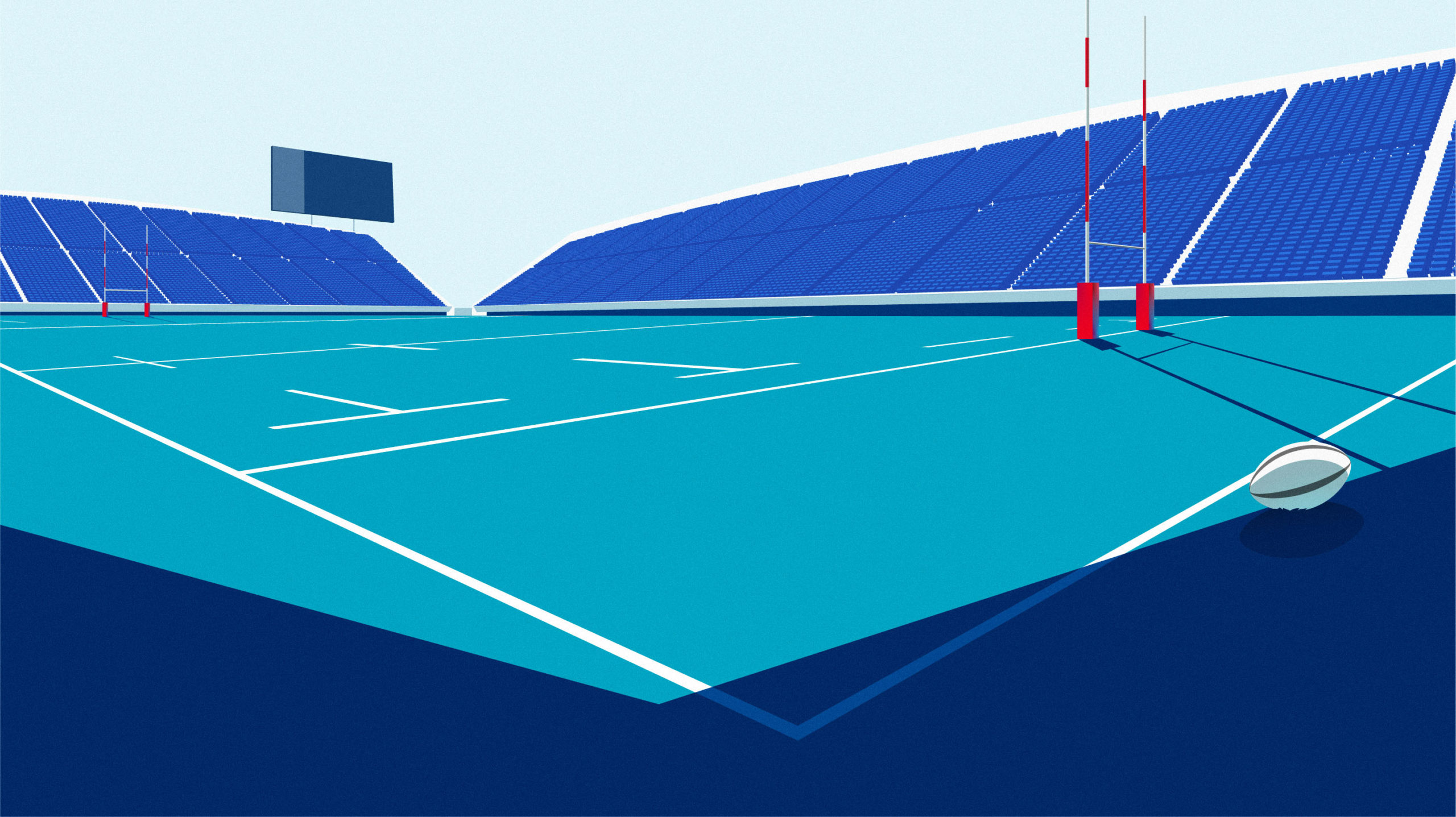冬の花園、過去5大会で3度の全国優勝。高校ラグビー界で"東のヨコヅナ"という異名を持つ東日本屈指の強豪校、桐蔭学園の勢いが止まらない。「名将論。」第2回のゲストは、コーチ時代も含め約30年に渡って同校の指導に当たってきた藤原秀之監督。近年の躍進の裏にあったもの、そしてリーグワンや日本代表にもOBを巣立たせた名将の哲学とは何か。リードラグビーが直撃した。
桐蔭を一段引き上げたメンタルのアプローチ
藤原監督は、「生徒たちにとって最善のもの」を常に探し求めてきた。
その中で近年の躍進の裏には、スポーツ応用心理学という武器、一人のキーマンの存在があったことがわかった。
「今、メンタル面をサポートしてくださっているのが、布施努先生という方なんです。布施先生はアメリカでスポーツ応用心理学を学んで博士号を取得されたドクターで、オリンピック・パラリンピックアスリートの指導もされたことがある方。その知見を現場に活かせる稀有な存在です。実際にセッションを受けてみて、私たちにはできないような衝撃的なものを教えてくださったので、お願いすることにしました」

画像:『桐蔭学園ラグビー部 勝利のミーティング』
布施氏の指導が本格的に始まったのは、2014年の花園予選で桐蔭学園が慶應義塾に県10連覇を阻まれた後、齋藤直人(現サントリーサンゴリアス)がキャプテンを務めた代から。戦力的にはそれほど恵まれていなかったチームだったというが、冬の花園で3度目の全国準優勝という結果を残した。
それまでは「夏や秋にはこうなるだろう」という藤原監督の予想と、チームの成長にズレがあったそうだ。
高校生はメンタルの浮き沈みが激しいもの。スポーツ応用心理学の導入によって、その浮き沈みの幅が小さくなり、夏や秋から冬にかけてうまくピークを迎えられるようになったという。
「本当にそれは10回やって10回できるのか?」
布施氏が具体的にもたらしたものとしては、選手たちが主体的に行うミーティング、そして最高目標と最低目標を設定する"ダブルゴール"という考え方がある。
「一番の目標に対して、その大前提にある"自分たちが10回やって10回できること"を設定しましょう、ということなんです。これはスーパープレーである必要はないんです。例えばボールを奪うビッグタックルが最高目標であるとして、大前提は前を見ることなのか、ストレートアップなのか、早いポジショニングなのか」
ポイントは、その目標は選手たちが自分の頭で考えなければならないということ。
「一方的に示されても納得感がないですし、指示を待ってばかりになってしまいます。それでは試合だけでなく、社会に出ても活躍できないですよね。私の役目はその目標を確認して、突っ込みを入れることです。本当にそれは10回やって10回できるのか、と。今は私が言わなくても、自然と周りの選手たちが指摘しあうような環境になっていますね」
こうしたアプローチによって「やるべきことが明確になり、余計なことを考えなくて済むようになった」という変化があったという。

写真:アフロ
桐蔭学園の試合を見ていても、局面で押し込まれる場面があっても基本プレーに立ち返り、決してあわてない姿が印象的だ。「大舞台では当然緊張はすると思いますが」と語る藤原監督だが、直近の花園決勝でも終盤の東福岡の猛攻を反則せずしのぎ切るなど、メンタル面の落ち着きが見て取れた。
積極的にラグビーの外にアンテナを広げる
もちろん桐蔭学園の強さはメンタルだけではない。
個々人のボールを持った際の推進力も目を引く。フィジカル面ではどんなトレーニングをしているのだろうか。
「単純に体を大きくするだけではなく、実践で使える持続性や柔軟性とのバランスを意識してトレーニングしています。体操的なアプローチも取り入れて、人間がもともと持っていた可動範囲を取り戻すようなイメージです。今はスポットのフィジカルコーチが3人いて、動作解析の専門家である手塚一志さんにもパフォーマンスコーディネーターとしてお手伝いいただいています」
ここにも優秀な外部専門家の存在があったようだ。「ラグビーの世界だけでは狭い」と藤原監督は積極的にラグビーの外、学校の外に目を向ける。「会ってみないとわからない」と気になる人がいれば話を聞いたり、セッションを受けるそう。
藤原監督の名将としての素質は、こうした知的好奇心の強さ、アンテナの広さにあると感じた。
また、桐蔭学園自体にも外部の人間を取り込む風通しの良さがあったようだ。藤原監督、そして長くタッグを組む金子俊哉コーチはともに東京の高校出身でOBではない。「良くも悪くも重鎮のような存在がいなかったのは大きいかもしれません」と藤原監督は言う。
ブレイクスルーは初めて花園決勝に上がった時
もう少し時間軸をさかのぼって藤原監督がブレイクスルーを感じたタイミングはいつだったのだろうか。
それは2005年度の花園で初めて決勝の舞台に上がり、準優勝を果たした時だという。「選手たちに引き上げられたんですよ」と目を細めて言う。
「スクラムハーフの櫻井朋広(NECグリーンロケッツ等でプレー)が主将だったチームの代ですね。とにかく櫻井の存在は大きかったです。一貫性がある。献身的にプレーする。ハートが強い。もう異常なくらいでしたね。彼のような選手には今後出会うことはないでしょう。大分出身で高校から入ってきた彼が、内部あがりの選手にムチを叩きながら引き上げてくれたんです」
結果を出したことで他校の見る目も変わった。
「花園が終わってGWのサニックスワールドユースで、大阪工大高の野上先生や伏見工業の高崎先生から声をかけていただいたんです。初めて野上先生の方から声をかけていただいて、『お前勝ち方つかんだやろ』と。高崎先生からは、『練習試合やろか』と言ってもらえました。花園の決勝という舞台に上がって、伝統校の監督さんからも認められて、これまでのやり方に一定の手応えを得ることができました。一方で優勝するにはまだ足りないな、とも」
花園優勝から逆算してシーズンの中に遊びをつくる
選手たちのメンタル面、短いスパンでの連戦、「近畿のチームを相手にする決勝は99.9%アウェー」と語る地の不利など、花園にはそこに至るまでの道程も含め特有の難しさ、勝ち方がある。

写真:PIXTA
今では花園の決勝で勝つ、という最終目標のためにシーズンの中であえて遊びをつくることもあるという。昨年のチームを例に解説する。
「サニックスワールドユース予選大会には、関東新人大会で優勝すれば出場の可能性があるために予選に参加しませんでした。出来ることなら参加したかった大会です。結論として参加できなかったために、あえて課題を与えなかった。そろそろ自分達で船を操船する時期かと思い、一度選手に船頭をさせた感じです。そして関東大会では苦戦。国体で沈没してくれたおかげで、チームも引き締まり全国大会予選に入りやすかった」
指導者はもっと「柔軟性」を持つべし
ここからは高校ラグビー界への提言を聞く。高校ラグビー人口はこの20年で4割減っている。競技人口減少に歯止めをかけるヒントは。
「ボール1個あればできるような、シンプルな形のラグビーがもっと普及すれば」とし、続いて他競技と人材をシェアしあえるような仕組みづくりが必要だと語った。
「他競技にいい人材は沢山いますよね。サッカーはあんなに競技人口がいますけど、その内半分でもラグビーをしてくれたら競技力はもっと上がるのになと。日本にはそういった文化がないので難しい面はあると思いますが、シーズンスポーツのようなシステムづくりは必要かもしれないですね。また、勝利至上主義に疲弊して小学校でやっていたスポーツを中学高校でやめてしまうようなケースも多く見聞きします。とにかく色々な選択肢を与えて、その中にラグビーも入っていれば」
また、他校の指導を見ていて「柔軟性が足りない」と指摘する。
「最近気になるのは、リーグワンに在籍しているOBが自チームの練習をそのまま持ち込んでしまっている例です。でもそれって、もともとできる選手たちがやっている練習なわけじゃないですか、高校生年代には強度も教え方も何段階か落としてアレンジしなければいけない。戦う方としても、これはリーグワンのシステムだな、とわかるのでつつきやすいんですよ」
「柔軟性」も藤原監督の指導哲学を読み解くキーワードだ。桐蔭学園に話を戻せば、新チームの選手たちにそれを求めている。
「成功した前年度のやり方というのは一番怖いんです。生徒たちにはそれはお前たちがやったんじゃない、それを疑えと言っています。ミーティングのやり方もそうです。新チームでは一度ミーティングの形を壊そうと思っていて。そろそろ言おうかなと思っているんです。こんなやり方じゃだめだぞ、と」
とニヤリと笑う。最後に名将の厳しさを垣間見た気がした。

写真:編集部
取材・文:竹林徹(リードラグビー)