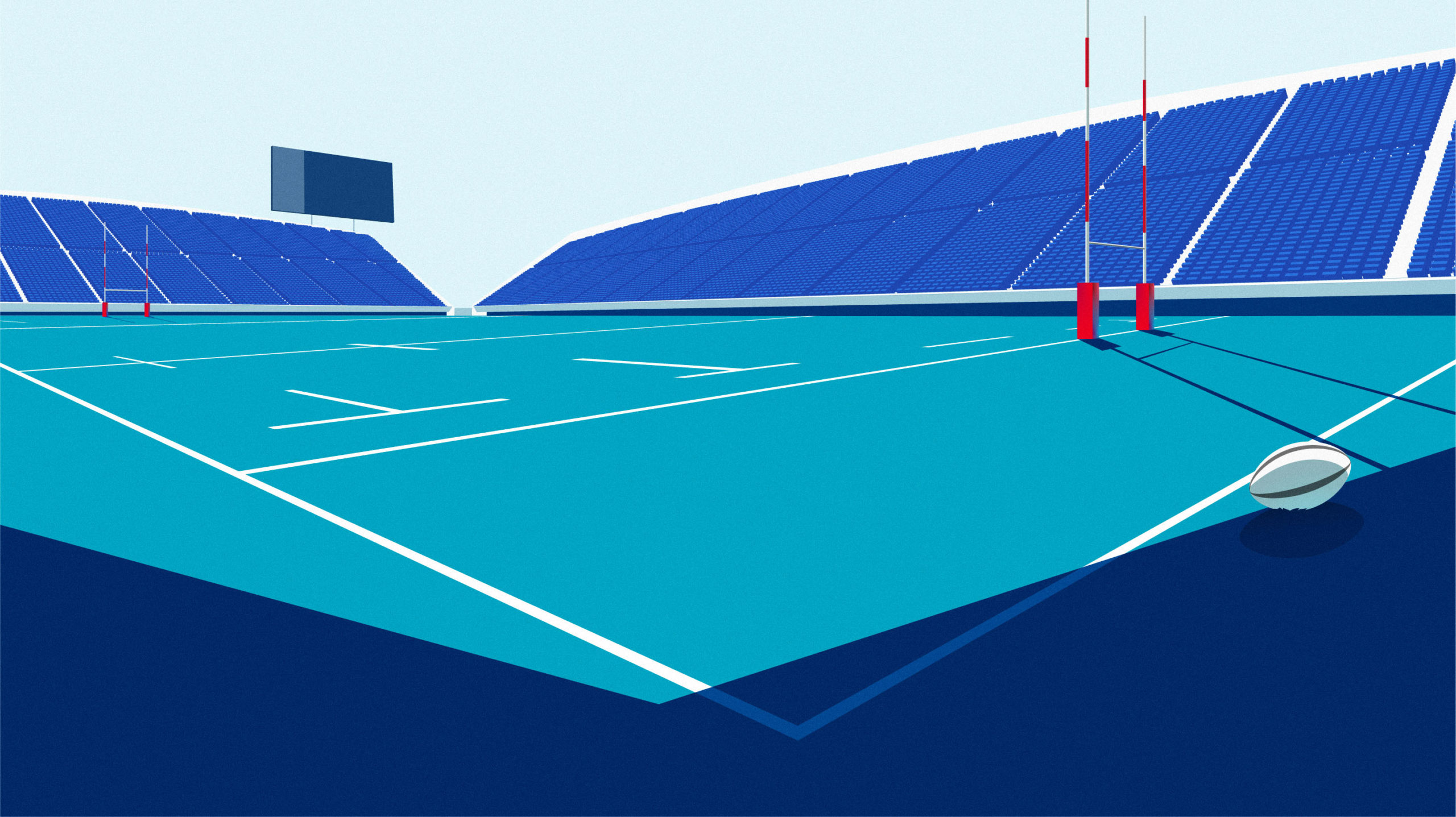フランスワールドカップでの切れ味鋭い解説でファンになった方も多いだろう。元日本代表で、現役引退後は追手門学院大学女子ラグビー部や母校早稲田大学ラグビー部での指導に携わり、現在は解説者として活躍する後藤翔太さん。トップレベルでのプレー経験と指導者時代の試行錯誤を血肉化し、そのラグビー観を著書『ラグビー 勝負のメカニズム』(KADOKAWA)にまとめた。刊行にあわせラグビーのメカニズムについて語ってもらった。
ラグビーは「スコア確率」を高めるゲーム
後藤さんのラグビー理解のベースには、追手門学院大学女子ラグビー部で指導した7人制ラグビーがある。
人数が少なく、試合時間も7分ハーフと短いが「ラグビーの要素が高濃度で抽出されているエスプレッソのようなもの」といい、そこから学ぶべきものは多いようだ。
指導力に自信があったパスを教え、どんどんボールをつないでディフェンスラインを攻略するラグビーを目指していた。しかし、女子7人制では男子に比べて速いパスが難しく、ディフェンスが対応しやすい。そして自陣でパスを回していく間にターンオーバーされれば、一気にピンチになる。
「ボールを持ったチームが有利」という常識が通じなかったのだ。
「全然パスでディフェンスラインをブレイクできない、勝てない。考え方が間違っていたんじゃないか、と悩みました。そこからですね、試合のデータもとってラグビーの全体について考えるようになったのは」
その過程で、そもそも1試合のボール保持回数は両チーム均衡している、ということにも気づいた。
具体的な数字を出して説明してくれた。
「よく考えると当たり前のことなんですが、7人制はトライした方が次のキックオフを蹴って相手チームに渡すので、1試合に両チームがボールを持つ回数は同じになるんですよ。これは1試合14分間でだいたい10回ずつです。ボールの保持時間も、強いチームほど時間をかけずに一気にトライをとりますし、実力差があったとしてもあまり変わらないんです」
トライをした後のキックオフで再びボールを手にするというルールの違いはあるが、15人制も捉え方は同じだ。
「15人制では得点の回数差だけボールを持つ回数は増えることになります。なんですが、やっぱりテニスのようなラリーがあって両チームのボールを持つ回数はだいたい1試合40前後に落ち着くんです」

写真:AC
「その決まっている回数の中で、何回スコアできるか。勝敗をわけるのは、そのスコア確率ということです」
大事なのはスコア確率。逆に、TV中継のスタッツに表示され、ゲームの優劣を示すために引用されることも多い「ボールポゼッション(ボール支配率)」は本質的なデータではないということだ。
日本はアルゼンチンを「射程圏」に入れてしまった
スコア確率を高めるためには、トライの「射程圏」に入り、相手は圏外に押し込みたい。
トライの射程圏とは、一律に数値化されているものではなく、チームの総合的なラグビーの強みによって可変する。
直近のワールドカップフランス大会、日本代表の最終戦となってしまったアルゼンチン戦(27-39で敗戦)では、まず射程圏に入られる回数が多かった。言い換えると、アルゼンチンを射程圏外に追い出せる回数が少なかった。また、その射程圏でのプレーの起点がアルゼンチンの得点確率の高いラインアウトからだった。これらが敗因になったという。
「アルゼンチンの最もスコア確率が高いプレーは、ラインアウトからでした。日本が前半と後半の入りにとられたトライもそうですよね。1本目のトライは、ラインアウトからモールを組まれ、次のバックス展開でタックルを外され一気に失点しました。
その前のプレーを振り返ると、日本はアルゼンチンのキックオフをキャッチして、そこからタッチに蹴り返して出してしまったんですね。TVの解説でも指摘しましたが、あそこはインフィールドに蹴り返してアルゼンチンにカウンターアタックをさせるべきだった。攻撃起点によるスコア率の違いを意識して試合を組み立てるべきだったと思っています」
簡単ではないが、私たちも「今チームがプレーしているエリアは射程圏内、それとも圏外?」「スクラム、ラインアウト…このセットプレーはスコア確率が高いだろうか?」などと考えられると、観戦の深みが増しそうだ。
スコア確率、射程圏といった用語も含めて、後藤さんの視点はこれまでのラグビー界になかったもので面白い。受け売りではなく「基本的に自分で結論を導き出せるまで考えます。そうしなければ、ここまで高度化したラグビーを瞬間的に捉え、解説することはできません」という。
今回のインタビューで触れられたのは、そのラグビー観の一端にすぎない。
著書『ラグビー 勝負のメカニズム』(KADOKAWA)では、図解付きでより詳細に解説されているので、興味のある方はぜひそちらも手にとっていただきたい。昨シーズンのファイナルや強豪チームについての分析もあり、新シーズンがこれから始まるリーグワン観戦にもうってつけの一冊だ。
取材・文:竹林徹(リードラグビー)